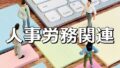※本記事はあくまで参考として私見を述べたものであり、実際の投資や資産運用については、ご自身の判断で行って下さい。
新NISAがスタートしてしばらく経ちます。
“やらないと損”だとか、“儲かった”というようなネット上の煽り文句の一方で、相場の急落などもあり、びっくりした投資初心者の方も多いようです。
今回は、投資の基本となる積立投資について、コメントしたいと思います。
まず、あたり前のことですが、投資には、「元本割れ」などのリスクが伴います。逆にリスクを取るからこそ一定以上のリターンがあるとも言えます。
また、世の中には短期間で大儲けしている人がいないわけではありませんが、普通の人には難しく、また、目標にするものでもないと考えます。
ということで、あくまで老後資金の準備など中長期的な将来を見据えて投資する手法としての積立投資の試算を行っていきます。
【私が思う“手堅い”積立投資】
1.長期を前提に積立投資を行うこと
2.個別株ではなく投資信託を買うこと
3.アクティブファンドではなくインデックス投資に徹すること
4.生活に影響のない範囲の少額で行うこと
5.運用成績に一喜一憂しないこと
1、2、3については、投資の基本である「長期分散投資」の原則に従うものです。短期的に上昇する一部の銘柄に投資して利益を上げることもできるかもしれませんが、先程申し上げたように、それをみんなができるわけではないので、手堅い投資法として、長期分散投資を行うことがよいと考えています。
また、3については、インデックスよりも高い運用利回りを目指すアクティブファンドもありますが、その分手数料も高くなります。
長期で見ると、最終的にはインデックスファンドの方が平均で上回る、と書かれた書籍も見られますので、ここではインデックス投資をお勧めしておきます。
※インデックス投資とは、日経平均、S&P500、全世界株などの指数に連動する運用を目指す投資手法で、こうした運用を行うファンドをインデックスファンドと言います
4、5については投資にのめり込まず、過度な期待を抱かず、ほったらかしにするくらいの気持ちで始めるのが気楽でよいと思います。
では、具体的な試算を行ってみます。
毎年12万円(月1万円)を積み立てたとき、一定年数経過後にいくらになるのか、を見ていきます。
前提の置き方は以下のとおりです。
1.積立額 : 年12万円
※実際には毎月積み立てをすると思いますが、計算を簡便にするため毎年の積立とします
2.利回り前提 : 6%
※無リスク資産の利回り1%にリスクプレミアム5%を上乗せしたと仮定します
試算においては、年金終価係数を使用します。年金終価係数は、運用年数と前提となる利回りで決まる係数ですので、使い方を覚えておくと大変便利です。
(ネットで試算サイトもあります)
【試算1】20年運用(45歳から65歳、55歳から75歳など)
12万円 × 36.786 = 約441万円(運用利益201万円)
【試算2】30年運用(35歳から65歳、45歳から75歳など)
12万円 × 79.058 = 約948万円(運用利益558万円)
【試算3】40年運用(25歳から65歳、35歳から75歳など)
12万円 × 154.762 = 約1857万円(運用利益1377万円)
実際に、世界株指数や米国株S&P500指数に連動するインデックスファンドであれば、過去実績から考えると、上記の利回りを期待できると言われています。
(もちろん暴落することもあるので、期間によっては下回る可能性もあります)
また、NISAでの積立が有利なのは、運用利益が非課税になることです。
上記例3であれば、運用利益1377万円に対し、NISA口座でなければ原則約20%の約275万円の税金がかかりますが、NISA口座だとこれが非課税なので、手元に残ります。
時間の経過による「複利効果」が期待できるので、少しでも早く始めることが一番大事になります。
特に若い方は長く運用できるので、そのメリットを活かす観点からは少額でも早く始めた方がよい、ということになります。
繰り返しになりますが、投資にはリスクを伴います。
経済的に許容できる範囲であり、かつ心理的に耐えられる範囲内のリスクであることを大前提に、みなさまの資産運用をお考えいただく上で、本稿が参考になれば幸いです。